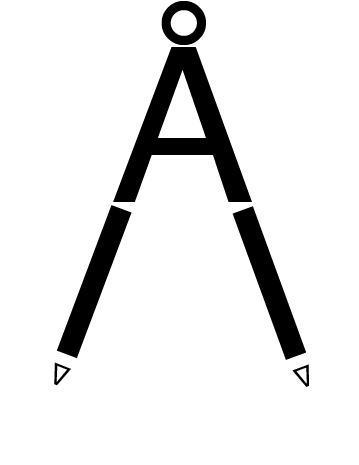医療に携わる方々へ、たったひとりの歓声を贈る。
たったひとりの歓声
この世界には、届けられるべき歓声がある。
ときにそうした歓声というのは、極端に小さかったり、
ひとが心にそっと秘めていたりするので、気づかれていなかったりする。
そうした歓声を見つけ、届けるべき人に届けること。
その意味を人と分かち合うこと。
それが僕たちのような、メディアに携わる人々の仕事だ。
たとえそれが、たった一人の歓声であったとしても。
@ebononom
この動画を見てほしい。これはロンドンの中心部で繰り広げられているNHS(国民保険サービス)に従事する人に向けられる歓声だ。"Clap For Our Carers (#clapforourcarers)" と呼ばれる運動で、時間をあわせ、街中の人が自宅の窓を開け、社会的距離を保ちながら医療に従事するすべてのひとに歓声を届ける。この運動を始めたのはアンヌマリー・プラス(Annemarie Plas)というオランダ出身・ロンドン在住の女性だ。彼女の母国で似た運動があったことから、ロンドンでも始めたそうだ。またたく間にこの運動は広がった。毎週木曜日の夜8時、家のバルコニーで拍手したり、踊ったり、歌をうたったりしてNHSの医療従事者への感謝と激励が捧げられる。僕がちょうどロンドンを出国した、1ヶ月ほど前に第1回が行われた。上の動画は、バービカン・センターに住む友人が撮影したものだ。
ロンドンという街は、今の状況の中で本当に歓声を届けるべき人のことを、多くの人が共通認識として持っている。またひとつ、ロンドンが好きになった瞬間だった。
日本はどうだろうか?
黙っていても何も変わらないので、僕は僕の仕事をしようと思い、この文章を書いている。 届かない歓声を、自分なりに届くべきひとに届けること。いつもやっていることを、やってみようと思う。
今回はとある男性が体験した、呼吸器外科の医療現場について書いてみたい。 日本中の病院で今、まさに戦場のような場所になっている科である。 少し長くなるが、ぜひ最後まで読んでみてほしい。 そしてもしここに書かれている内容が、歓声と感じられたら、届けてほしい。 本来歓声が届けられるべき、最前線で医療に携わる人々へ。
伝染病は、世界に残された数少ない純粋な冒険のひとつだ。
――ハンス・ジンサー(チフス菌の発見者)
微増
病気というのは、前もって予定を立てて患者を襲うものではない。たいていが「むちゃぶり」である。医療というのは、そんなむちゃぶりに、いつも全身全霊を傾け、現場で戦い続ける医療従事者の方々のひたむきさによってのみ、支えられている。
「なんかちょっと、大きくなってきてるみたいなんですよね」
30代後半の男性の眼前にあるディスプレイには、その男性の肺の輪切り写真が映し出されていた。数週間前にうけた人間ドックで撮影されたCTだった。
その男性にはかれこれ4年間ほど経過観察していた肺の疾患があった。それは小指の爪の先っぽくらいの、ちいさな「何か」だった。医師の最初の診断は「子どもの頃にかかった肺炎の“しこり”か何かでしょう」というもので、1年に2回程度の「経過観察」という診断がされていた。
男性は病院に通うたびにその「何か」の経過を見ていた。不安ではあったが、CTに映るそれはいつ見ても何も変化がないので、それほど心配してもいなかった。
「4年前と比べると、少し大きくなってきているように見えるんですよね。どうでしょう、念の為、呼吸器外科で診てもらっては?」
腫瘍が何らかの形で大きくなる、つまり、身体の中で量を増やすということが、悪性腫瘍つまり癌であるかどうかの判断基準のひとつになる。
その男性はそのときに初めて知ることになるのだが、じつは現代の最先端の医療技術をもってしても、その「何か」ががんであるかどうかを完全に証明することはできないのだ。腫瘍が非常に大きく、明らかに短期間で体積が増加している、転移がみられるという状況であれば(もっともそれは非常に救いがたい状況ではあるが)、ほぼ確実な診断をすることは可能だ。しかし、小さくかつ数年単位で見てようやく微かな差異がわかるような腫瘍を判定することは難しい。「穿刺」して組織を取り出し、直接調べるのも難しい。対象が小さすぎると判定が難しいだけでなく、そもそも成功するかもわからない。がんの発見に特化したCTの撮影方法「PET-CT」などをはじめとする、多角的な検査を行い、予測の確率を少し上げることはできる。しかし、完全に「これは癌ではない」と判定することは、外科的手術を除いては不可能なのだ。
タバコ
「思い切って、手術しましょうか」
場所は変わって、ここは先の医師に紹介された、別の病院の呼吸器外科の診察室だ。
この男性は1ヶ月半先、海外転勤が決まっていたこともあり、呼吸器外科の医師は手術をアドバイスした。
「万が一ってことがありますし。すっきりした気持ちで旅立たれたほうが、心身の健康にもいいでしょう」
手術前後の入院と経過観察も含め、手術から退院までは少なくとも1ヶ月程度は見ておく必要がある。日程的にはギリギリだった。
その医師は、その男性が人生の中で出会った、最初の外科医だった。
外科医というのは、治療における最後の現場に立つ。つまり自分にメスを入れる人だ。
男性は、正直なところまいっていた。海外転勤の準備は、家族も同伴となるとビザの準備やらで大変なのだ。人生でも5本の指に入るような大変な時期に、厄介なことが重なり、心身ともに疲弊していたのだ。 しかしこの医師の意外な一言が、男性を勇気づける。
「タバコは吸いますか?」とその医師が訊いてきたので、男性は「かつて吸ってました」と答えた。すると、その医師は「まあ、吸いますよね、若い頃って。僕も吸ってました」と返答した。
男性にとってその返答は思いもよらないものだった。彼は呼吸器外科の医師だ。タバコが肺に悪いことを知っているのは当然だし、そもそもタバコが原因で癌になった患者を何百人も診てきたにちがいない。
「先生でも、タバコ吸うんですね」
「ええ、まあ。はは、どうしようもないですよね、タバコって。もうやめちゃいましたけど」
意外な返答だった。
医師、それも自分の肺にメスを入れるかもしれない医師がかつてタバコを吸っていて、喫煙者の気持ちを煙たがるどころか、「どうしようもないこと」として受け止めていることに、男性はなんとも表現し難い人間味を覚えたのだ。
そうなのだ、タバコというのは、どうしようもないものなんだ。
人間の感情と、とてもよく似ているものなのだ。
男性はその日のうちに手術同意書にサインし、手術することを決めた。
この会話がなかったら、先送りしていたかもしれない。男性には、転勤先の海外の病院で治療を受ける選択も残されていたのだから。
手術
手術当日まで、風邪をひかないように慎重に家で過ごし、男性は手術前日に入院した。
手術は早朝から準備に入る。6時に起床し、7時には検診を済ませ、素っ裸の上に手術用のガウン一枚という姿になっていた。
面会に来てくれた家族と少し話し、男性は手術室に入った。
手術室は思ったよりも陽気なムードだった。Tofu Beatsというミュージシャンのポップな曲が鳴っていて、手術を担当してくれる医師たちも「手術、初めてですか?」と気さくに話しかけてくれるし、冗談なんか言いながらにこやかに笑っている。男性は自分のそれまでの仕事を思い出し、ここにいる人たちが本当のプロフェッショナルだと確信した。この人たちはこのチームで、もしかすると昨日にも生死を左右するような現場をやり終えたばかりかもしれない。過去には辛い死別もあったことだろう。それでも、彼ら彼女らはみな、いつもと変わらない自分でチームとしてそこにいるのだ。その日の、目の前にいる患者の人生を救うために。
その男性の手術は、片肺の上部の一部を切除するというものだった。手術は脇腹のあたりを大きく切開して行われる。最近は内視鏡などを用いた、ダメージの少ない「低侵襲手術」も行われる場合があるが、心臓が近く、重要な血管が多数ある場所では、きちんと目で見て手術を行ったほうが危険性が低いらしく、切開部は大きくなるのだそうだ。
手術台の上で背中を丸めて寝転がる。麻酔はふたつ。背中の脊髄と腕の血管だ。腕に麻酔の注射針が刺されると、男性の意識は途絶えた。
手術が終わり、麻酔から覚めると、そこは地獄だった。
男性は泳ぎが得意でもあり、人生で溺れたことはなかったが、そのときの状況を溺れているような感覚として記憶していた。どれだけ呼吸しても呼吸をしていないような気持ちになるのだという。おおきく息をしようものなら、激痛が走る。それは予想に難くない。ほんの数時間前そこにあった肺が切り取られたのだから。身体にはあちこち管がつけられ、自由も効かない。男性は即座にパニックになった。しかし次の瞬間――。
「もう、大丈夫ですよ」
ひとりの女性医師(だろうか?)がそう言って笑顔で男性に語りかけていた。その表情には、その男性の手術が成功に終わった達成感のすべてがあった。もう自分は大丈夫なんだ、そう確信したとき、男性のパニックはおさまった。
あれほど説得力のある表情を、その男性はそれまでの人生で見たことがなかったと述懐する。近いもので言えば、プロアスリートが自らの記録を塗り替えたときの、歓喜に満ちた笑顔がそれに近いかもしれない。それもテレビの中での出来事だ。自分がそんな表情をしたこともなければ、男性の周囲はそんな表情に満ちた環境でもなかった。
ひとは生きて仕事をしていると、素晴らしい仕事をしているチームに出会うことがある。そして自分もそのメンバーになりたいと思う。しかし、そのチームの人たちの厳しさや、自律心を知るほどに、そのチームの敷居がいかに高いかを思い知ることになる。ある人は目を背ける。ある人はそれを機に自分を律し、変わる。より素晴らしい仕事をするために。そんな瞬間を目の当たりにしたときに似た気持ちで、男性は手術室を出た。
拷問
次に男性は、集中治療室のような部屋に移された。薄暗い部屋で、相変わらずの息苦しさが続いていた。
両親が面会に来てくれたが、あまりの激痛でうまく接することもできなかったという。妻だけが男性の手を握り続けてくれていた。
しかし、しばらくすると再び男性は病室でひとりになった。
なにもできないでいた。正確に言えば、あまりの激痛で、文字通り、なにもすることができないのだった。
この男性の激痛を、自分の書き手としてのやり方で分かりやすく描写してみる。
肺というのは、身体でもっともよく動いている臓器のひとつだ。なぜなら、人間は生きている限り呼吸をするからだ。1回の呼吸を見てみよう。呼吸というものは、体内の二酸化炭素と、外の空気の酸素を交換する働きだ。呼吸の際には、横隔膜と呼ばれる筋肉が肺全体を減圧することによって口から空気を吸い込んで行われる。そして肺の中には「肺胞」と呼ばれる微細な風船のような器官がある。一度の呼吸で、この肺胞は大きく膨らんで表面積を最大化し、口から吸い込まれた空気から、酸素を血中に取り入れる。その総表面積は、個人差はあるが、100平方メートルにもなるとも言われている。ちょうど小学校にある25メートルプールの半分くらいの広さだろうか。
このダイナミックな動きがある中に、数分前に閉胸し、縫合したばかりの皮膚があり、筋肉があり、張り巡らされた神経があり、切除された肺がある。それらが息をするたびに、大きく動く。その痛みは、まるで背中にムチを打たれているような激痛だという。呼吸を小さくすれば幾分ましだが、小さな呼吸のままでは酸欠になる。呼吸は変えられない。この状態で、集中治療室で48時間。当たり前だが、一睡もできず、身体も動かすことはできない。できることと言えば、おしっこぐらいのものだ。尿道に差し込まれた管を通して用を足す。奇妙な感覚だったという。
そんな状況におかれた男性は、すぐさまナースコールを押すことになった。
「すみません、あまりにも痛いので、痛み止めを打ってもらえませんか?」
看護師がやってきて痛み止めを処方した。
しかし、これがまったく効かなかった。
男性は緩和されない痛みに耐え切れず、数分後にはすぐさまナースコールを押したという。するとすぐに他の痛み止め薬が投与された。それでもまったく痛みは消える気配がない。男性が再びナースコールを押すと、「もっとも強力」という、乳白色の小さな点滴が処方された。しかし痛みにはまったく変化がなかった。再びナースコールを連打する。するとかけつけた看護師は、男性にこう言った。
「痛み止めはもう打てません。あなたに投与されている量は、もう限界の量に達しています」
おそらくだが、このとき男性には通常では昇天してしまうような量の鎮痛剤が処方されていたのだろう。しかし一切効いている感覚はない。男性は絶望した。そして絶望するたびに、ナースコールを押した。
「すみません、あまりにも痛くて…助けてください。本当に」
気づけばその男性は、看護師に命乞いをしていた。生まれてはじめてのことだった。人間というのは、もともと強くはできていない。打たれ強さも経験の賜物なのだ。何か政治的な理由、たとえば戦時下の国でテロリストに捕まり、拷問でもかけられたりした経験がない限り、この状況の中で正気を保つのは不可能だろうと男性は話す。
そうして病室の時計の針だけを追いかける48時間はなんとかやりすごし、男性は一般病棟に移った。 痛みは変わらなかったが、限界に達したのだろう、男性は気絶するように眠った。そして起きるとふたたび激痛が走り、絶望することを繰り返していた。
問題児
一般病棟でも男性は、痛みが出るとすぐにナースコールを押していた。解決することはないが、自分の痛みを分かってくれる誰かが男性には必要だった。それほどに辛く、孤独な激痛だった。しかし状況は変わらない。男性には常に、限界量の痛み止めが処方されていた。耐えるしかないのだ。一体この痛みはいつまで続くのか。男性は不安と苛立ちをつのらせていた。そんなとき、廊下から声が響いた。
「看護婦さあーん、ナースコール押してもぜんぜん来てくれなーい。一体どうなってるんですかあ〜この病院はあ〜」
どうやら厄介な患者がいるようだ。大声で、だらだらとした口調でクレームを言い続けている。あまりに長く続くので、時折医師や看護師が鋭い口調で静止する声も聞こえてきた。
大人げない人もいるものだ、と男性は思ったが、そのとき、自分がしていることもその厄介な患者と大差ないことに気がついたという。痛みが出れば無意味だと分かっていてもナースコールを押してしまう。そうして看護師の時間をむやみに奪っていたことに気づいたのだ。
痛みの中でこそ、わかることもあるのだ。
男性はその日を境に、ナースコールを押さないようになった。
しばらくすると男性は歩くようになった。看護師に支えられ、トイレまでの5メートルを歩く。到着まで、5分程度かかった。分速1メートル。ちなみにその男性の小学校の頃の50メートル走の記録は7秒ちょうどだったそうだ。
時間とともに、男性は自分の身体の回復力に驚くことになる。男性はその翌日には病室はもちろん、病棟も歩き回れるようになった。まだ身体は痛み、やっとのことで歩いていた。しかし眠れなかったり、耐えられないということはなかった。
男性は、ふと問題児の患者のいる病室の前を通りかかった。開け放たれた病室には、もう看護師にすら見捨てられ、誰にも構われなくなったことにふてくされているんだろう、ひとり部屋でうつむき、ぶつぶつ言っている中年の男が視界に入った。
患者も、入院生活の中で成長することが求められる。病院の住人として、ふさわしい振る舞いというものがあるのだ。そして中には成長しない患者もいる。そんな患者たちに囲まれて毎日を送るのが看護師の日常なのだ。
すごい仕事
男性が病室に戻ると、執刀をしてくれた医師が検診に来ていた。男性はこれまでの一部始終を話し、看護師さんに本当に申し訳ないことをしたと言った。医師は笑っていた。
「手術後の痛みは、激痛なんですよね。その人の体の中でだけ繰り広げられる、孤独な戦いなんです」
手術から4日後、男性は退院することになった。案外退院は早い。他にも多くの患者がいるのだ。
退院の日、男性は自分の面倒を見てくれた看護師全員に感謝の言葉を伝えた。
「よかったですね、おだいじに」とみな、笑顔で送り出してくれた。
それからしばらくして、腫瘍の分析が終わり、結果が告げられた。
それは悪性の腫瘍、つまり癌だった。
もしも、あの医師の英断がなければ、もしも検査を受けて見つかっていなかったら――。
ある別の医師の話だが、その男性は10年後にはこの世にはいなかったかもしれないという。
もちろん癌は全身病だ。これからも慎重に付き合っていかなければならないことも分かっていた。男性がそんな不安を口にすると、医師は言った。
「あなたはもう、がんでは死ねませんよ。もしものことがあっても、僕らが見つけて治しますから」
命のやりとりを昼夜繰り広げている、現場の医師の言葉は、強い。
そして患者は、その医師の言葉があることで、希望を持って明日を生きていくことができる。
すごい仕事なのだ――。
さて、この男性は、もうおわかりかもしれないが僕のことだ。
僕は幸いにも命拾いした。それほど書いても面白い内容ではないので、今まで仲の良い友人にしかこの話はしてこなかった。
でも、新型コロナウィルスのパンデミックを前にして、ここに書いておこうと思った。どれだけの人に読まれるか、本当に意味があるのかは正直、分からないが。
新型コロナウィルスも、肺がんと同様、重症患者は肺炎という肺の疾患を発症する。僕のような無症状の肺がんの手術とはまったく違う病気だが、激痛だろう。だからその体験記を自分の言葉で綴ろうとする人たちの心境もよく分かる。
しかし僕がここで書いておこうと思ったのは、その痛みの怖さのためではない。医療従事者の仕事に触れたひとりの人間として、その事実をひとりでも多くの人に知ってもらいたくて書いたつもりだ。
新型コロナウィルスの予断を許さない戦場で今も仕事をし続けているのは、ここに書かれている呼吸器科の医師や看護師を含む、医療従事者の方々だ。
新型コロナウィルスは、人類にとって未知の感染症だ。院内感染を防ぐために細心の注意をはらいながらの治療が必要になる。医療資源の枯渇、医療崩壊の危機、過労、状況の深刻さに伴う医療従事者の方々の心労は計り知れない。
しかしテレビをつけると、不完全な調査によって即席でつくられたような内容であるため、結果的に視聴者の恐怖を煽るためだけに終始している報道であったり、芸能人や学者をひっぱりだし、「この国はだめだ」と喝破しているものが目立つ。
それも必要な仕事なのだろう。
でも、本当に必要な歓声が、もっとこの国に満ちていても良いと思う。
この国を守るために、この今も現場で本当の戦いをしている医療従事者の方々にこそ、歓声を向けてほしいと思う。
患者ひとりひとりが、自分史上最悪の戦いをしている。そんなひとしかいない場所で、現場の医師や看護師は、最前線で戦い続けている。ひとりでも多くの人を救うために。その姿勢に患者として感銘を受けた経験がある人はぜひ、こんなふうに発信をしてもらいたい。
彼ら彼女らは、今、この国を本当に守ろうとしている人たちなのだから。
彼ら彼女らの仕事は、
今こそ歓声が届けられるべき、
本当にすごい仕事なのだ。